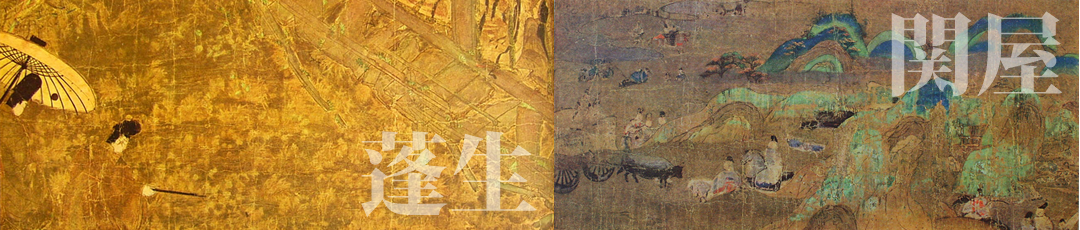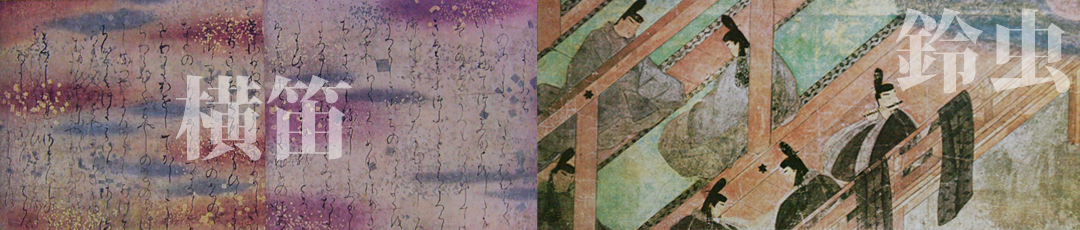ここで考えたい大きな問題があります。それは、18世紀の中ごろ、徳川という時代に、宣長ががなぜ「もののあはれ」などと言い出したのか、という問題です。「もののあはれ」が日本古来の存在論なのであれば、それは半ば常識なはずで、空気のようなものだったはずです。なぜ、ことさらに言い立てる必要があったのか、ということです。
それはおそらく、宣長のもうひとつの用語「からごころ」と大いに関係のある問題でもあるかと思います。「からごころ」とは万物の本質、原理原則を人間の理性で追求していく姿勢や態度、つまり原理主義のことです。原理主義が漢籍つまり大陸からの書物に多く見られ、当時の日本人がそれを無条件に有難がることを煙たがって宣長は「からごごろ」と呼びました。単に大陸趣味、シナ趣味のことを言ったわけではありません。
「からごころ」はもののあはれ、つまり関係の存在論とは対極にあると言うことができます。けれども、ここが肝心かと思いますが、宣長がもののあはれを確認するためにとった研究態度は「からごころ」の方法であり、言い方を変えると西洋近代的方法に他なりません。
小林秀雄、また、西尾幹二氏が著書「江戸のダイナミズム」でおっしゃっていることですが、徳川時代に近代はすでにありました。ただし、それがいつから始まったものであるかはさまざまに議論のあるところかと思いますが、ともかく近代は明治維新によって外からもたらされたものではなく、そのかなり前から日本では始まっていたということなのだろうと思います。
宣長は「からごころ」を否定的な文脈で使っています。当時、もののあはれが失われつつあってそれを嘆いたということではなく、近代化の台頭に宣長は危機感を抱き、源氏物語を再発掘してもののあはれを強調したのではないかという気がします。
日本人古来の存在論は、西洋ならびに大陸・中華のあるなしの二元論ではなく、道理というものがどうしようもなくあらかじめにあるそのうえでの重層的関係多元論です。言ってしまえば思慮と思いやりにあふれた、違う視点でいえば、結論を出す、決断をするということがどうもしっくりこないといった性格です。宣長はそれを、もののあはれの理論を使ってやまとごころとして明確な思想にしようとしました。ということはすなわち、なにか、その日本古来の存在論とそぐわないものごとが少なくとも宣長の時代にはびこっていたということに他なりません。
日本古来の存在論とそぐわないものがいつから始まったものかはわかりません。ただ、私の見当としては、室町の末期から戦国の時代、そして織田信長の比叡山の焼き討ち、楽市楽座でかたまったものだと思います。日本の近代はおそらくここから明らかなものとして始まったのではないかと思っています。
平安末期から朝廷の財政を圧迫し、また、活発な経済運動を行って利権化するようになる寺社勢力は、言ってしまえば今でいうカルト的な性格を持っていました。仏に抗うことはならない。御霊信仰とも関係があります。だいたい平安、鎌倉、室町初期は、政治とは祟りを鎮めることだといわんばかりの運営です。
周辺の寺社勢力ばかりが財を溜め込みます。それを織田信長が、きわめて科学的、功利的な判断で比叡山を叩きました。経済の恩恵が、これで広く一般化することになるわけです。おそらくはこれが日本の近代のはじまりであって、今に続いているのだと思います。経済が宗教からきっぱりと分かれる信長の経済開放があり、秀吉の安全保障の列島標準化があり、家康の通貨統一と封建体制成立の天下統一がありました。宣長が生きたのは、家康からすでにほぼ200年を過ぎた時代です。宣長が感じたのは、この近代というものの腐乱臭だったのではないでしょうか。その可能性は高いんだと思います。
宣長はやまとごころを大事にしたいと考えたわけですが、そのやまとごころを主張するために宣長がとった方法は、からごころつまり近代科学的な方法に他なりませんでした。何かを主張しなければと考えたときにとる方法は、からごころ以外にないことを証明しています。
民族性からいえば、日本は、まずは中華文明、その後の西洋文明とうまくやっていけるはずがない。しかし、中華文明と西洋文明とは否応なく侵犯してくる。それに抵抗するためには、近代文明の方法をとらなければならず、近代文明に長ける以外にありません。日本の文明史、文化史とはそういうものではなかったか、そして今後もそうなのだろうと思います。
拙稿をお読みいただき、誠にありがとうございました。