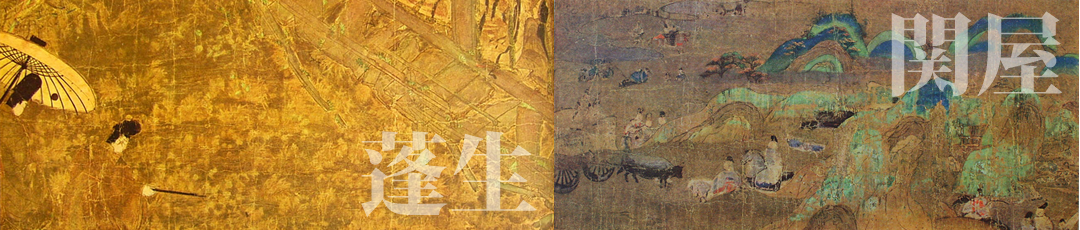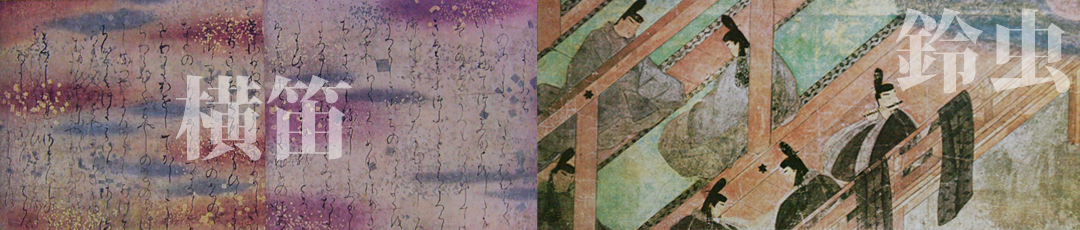年老いた女房が語り手としており、伝え聞いた話ですが、というかたちで書かれていることがまず源氏物語の独特です。それとは別に私がとりあげたいのは内容の書かれ方のことです。源氏物語というのはどの巻、どのエピソードをとってもおしなべて、仕方がないんだ、どうしようもないことなんだというところに話を落ち着けます。解決もなければ教訓もありません。
そんな話がどうして、飽きない、のでしょうか。私は書かれ方、言葉遣いに秘密があると思っています。次の引用をご覧ください。谷崎源氏からの引用です。桐壺が死に、その母親のもとに、帝の使いの靫負命婦(ゆげいのみょうぶ)がお見舞い、といいますか、生まれた息子(光)を宮中に戻せと命令させにいくわけですが、そのときに、桐壺の母が命婦に愚痴をこぼします。
●桐壺の母の愚痴
「子を思う道にくれまどう心の闇の片端だけでも、お話し申し上げて胸を晴らしとうございますから、公の御使いでなしに、一度ゆっくりお越しなされて下さいませ。この年頃は嬉しいことや晴れがましい御用でお立ち寄りくださいましたのに、こういう悲しいおん消息の御使いとしてお眼にかかりますとは、返す返すもままならぬ命でございます。亡くなりました娘は、生れた時から望みをかけていた娘でございまして、故大納言がいまわの際までも、『どうかこの人の宮仕えの本意を必ず遂げさせて下され。私が死んだからといって、意気地なく挫けてはなりません』と、くれぐれも言い置かれましたので、立派な後身を持たぬ女の人交わりはなかなかなことと存じながら、ただ遺言に背かないようにと思うばかりにご奉公に出しましたところ、身にあまるお志の幾重とも知れぬ忝さに、人に人とも思われぬような扱いをされるのを忍びながらどうにかお付き合いをしているらしゅうございましたが、朋輩方の嫉みが深く積もり、苦労の数々が増えてまいりまして、横死のような風に亡くなってしまいましたので、今ではかえってもったいないご寵愛をお恨み申しているようなわけでございます。これも親心の愚痴でございましょうか」
●上記の愚痴に呼応する、命婦が預かってきている帝の言葉
「わが心ながら、ああも一途に、人目をおどろかすように思いつめたというのも、やはり長くは続かない縁であったのかもしれぬと思うと、苦しい契りを結んだものだという気がする。自分はいささかでも人の気持ちをそこのうた覚えはないのだけれども、ただこの人がいたために、恨まれないでもいい人たちの恨みを負うたとどのつまりは、こんな具合に一人あとに残されて、心を取り直す術もなくて、いよいよみっともなく、頑なになったのであるが、前の世でどんな約束がしてあったのか知りたい」
桐壺の母も、とりわけ帝は、自分から発する心情ではなく、すべて人と人との関係をもってありさまを語ります。まわりくどくていいわけがましく、他人事のように聞こえるのはそのためですが、当人にはそんなつもりはありません。紫式部および登場人物にとって、そういうふうにしか世界はできていないのです。
紫式部および登場人物は、自分というものがまずそこにあって何かが生じるのではなく、関係というものが揺らぎながら動いていくことで自分というものは生じ、自分の心情というものができあがっていく、と考えています。つまり、これが源氏物語における世界観であって、人間の実存です。
したがって、源氏物語では、ある物事が起こった場合、その物事は必ず複数の視点から描かれます。対立した視点であることもあれば、並行並列した視点の場合もあります。単純な逸話なのに重層で厚みのある感じがするのはそのためです。
それらの関係の変化推移のありようが源氏物語のすべてであって、何か大きな事件が起こったり、それが解決したりするわけではない。源氏物語がべらぼうに長い理由もここにあります。ひとつのことを二方向からも三方向からも書くから、それは長くなるに決まっています。
考えてみれば、これは実にあたりまえの話です。源氏物語は、姫様に読み聞かせるために書かれました。それにはちゃんと目的があって、経験ということを全くしない、またすべくもない姫様に、世の中というのはこういうものだ、こういうときにはこう考える、こういうときにはこうするものだということを教えるためにまず書かれたものだからです。そして、肝心なことをひとつ申し上げれば、世の中とはこういうものだと教えるために書かれたものこそは存在論であって、他の何がいったい存在論なのか、ということです。次項、九に続きます。