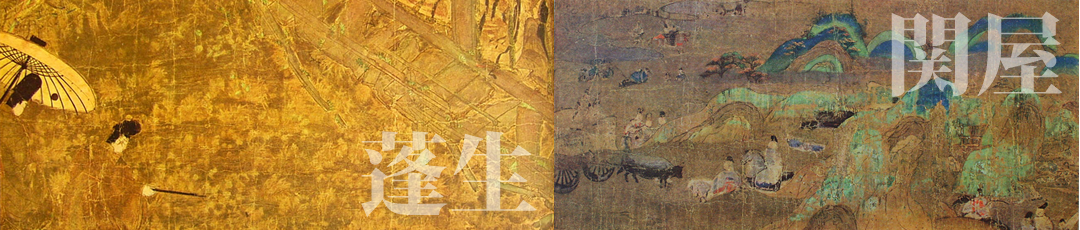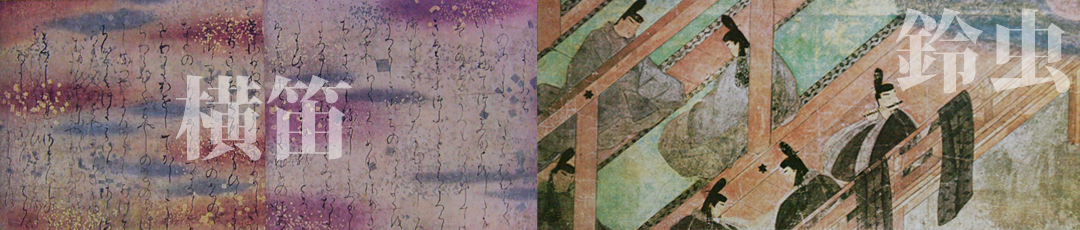「源氏物語は日本の国民文学か」というテーマでお話を申し上げます。
国民文学となると、まずは敗戦後すぐの、文芸評論家の竹内好氏らを中心に展開された「国民文学論」が有名です。サンフランシスコ講和条約(昭和27年・1952年)による日本の再独立を機として竹内氏らの「国民文学論」は展開されましたが、これは、独立国日本における、これからありうべき文学という意味合いでした。敗戦によって日本から朝鮮、台湾、沖縄が離れたことによる日本文学の領域のありようをはじめとした、政治色の色彩強い論です。
これからお話し申し上げる国民文学の意味はこれとはちょっと違います。素朴な意味での国民文学で、たとえばアメリカならマークトゥエインのハックルベリーフィンかな、とかヘミングウェイかな、とか、フランスならユゴーのレ・ミゼラブルかな、とか、そういったところでの国民文学です。
国民文学という用語について調べていて、ちょっと面白いことを見つけました。「国民文学」の辞書的意味です。同名の辞書でも版によって違うと思いますが、だいたい次の通りです。
大辞林(三省堂)
「一国の国民性・民族性がよく表された、その国特有の文学。また、その国で最も広く愛読されている、その国を代表する文学。」
大辞泉(小学館)
「一国の国民の諸特性をよく表現した、その国特有の文学。また、その国で広く国民に愛読されている文学。」
ブリタニカ国際大百科事典(TBSブリタニカ)
「一国の国民性または国民文化の表われた独特の文学とも、近代国民国家成立に伴ってつくられた文学ともいえる。いずれにしても国民または民族の固有の性格を高度に表現した文学のこと。」(抜粋)
広辞苑(岩波書店)
「①特に近代になって作られた一国の国民の特性や文化のあらわれた独特の文学。②国民の独立・統一・社会的進歩などの課題を意識し、国民の各層に広く読まれる文学。」
この中で興味深いのは岩波書店の広辞苑です。評論家の某氏が、国民文学といえば何かと問われて、こう答えたそうです。ドイツならゲーテのファウスト、ロシアはドストエフスキーのカラマーゾフの兄弟、日本は司馬遼太郎の「坂の上の雲」である。坂の上の雲、というところで何かピンとこずにいたのですが、わかりました。某氏は岩波の広辞苑に準拠していたのに違いありません。面白いと思います。
広辞苑の意味をとればとうてい源氏物語は国民文学とは言えないでしょう。そこで広辞苑は放っておき、私は辞書は大辞林が好きですので、これに準拠します。
はたして源氏物語は国民文学でしょうか。「その国で最も広く愛読されている、その国を代表する文学」であること、少なくともその中のひとつ、と言うことはできると思います。
去ること2008年は源氏成立ミレニアム、1000年記念とされた年でした。1008年が源氏物語にとってなぜ特別な年かというと、紫式部の、その西暦にあたる年の日記に、初めて源氏物語のことを取りざたしているらしい文章があるからです。時の帝、一条天皇の東宮生誕の祝いに宮中に上がっていた、おそらくは当時中納言の藤原公任が、このあたりに若紫はおられるかと式部に声をかけた。式部は、光君に及ぶ男君など誰もいないところでどうして若紫がいらっしゃるものかと思った、とある。それをもって源氏物語にとって重要な年としているわけです。ただし、この文章で、源氏の作者は紫式部だとされたわけではありません。式部が作者だと判断されたのはもう少し後、鎌倉時代の記録によります。
源氏物語ミレニアムだった2008年だけで90冊強の関連書籍が出版されています。いまも毎年20~30冊はコンスタントに出続けているようですから、人気があるということについては問題ないとして、重要なのは源氏物語が「一国の国民性・民族性がよく表された、その国特有の文学」であるかどうかだと思います。次項、二に続きます。