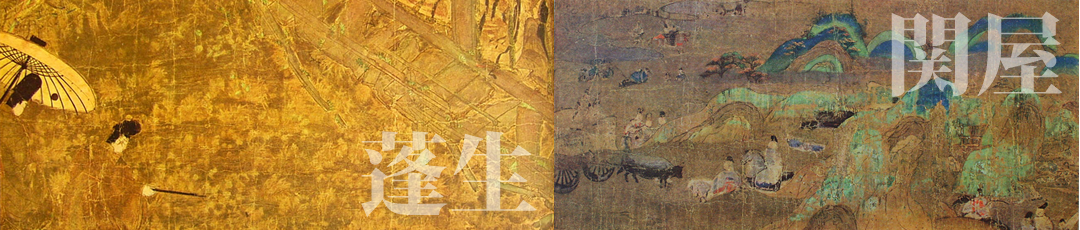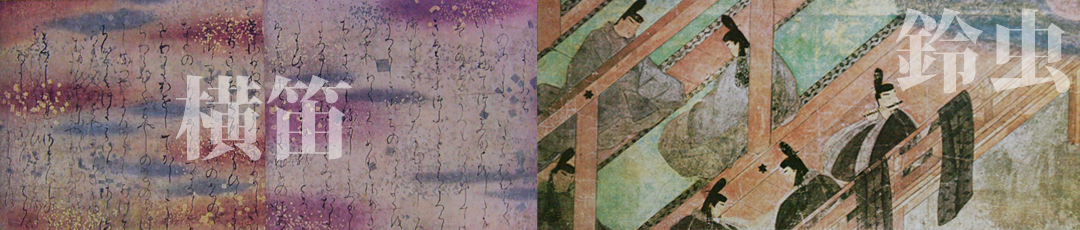前稿①で、源氏物語は言い訳だらけだということをお話ししました。今回は、なぜ、源氏物語の登場人物は言い訳をするばかりで謝罪をしないのか、ということについて考えたいと思います。
源氏の登場人物たちは、見事に謝罪ということをしません。決して謝らない。たとえば、葵上の臨終の際には生霊としてとりついた六条御息所は、紫の上の重体の際にも死霊で現れて物の怪としてとりつくわけですが、悲しませることの多かった御息所に対しても光君はこんな感じです。(引用はすべて新々訳谷崎源氏。「」はセリフ。‐‐は地の文)
まず、とりわけ六条御息所が恨みに思っているのは、こういうことです。
———————————————-
「中でも、存生中に人より軽くお見下げなされて、捨てておしまいになりましたことよりも、思う方とのお物語の折などに、私のことを憎らしい嫌な人間であったように、仰せ出されました恨めしさ、今はこの世にいない者だからと御勘弁なすって、他人が悪口を言うような時でも、それを打ち消し、庇うようになすってこそと、思いましたばかりにかような忌まわしい身になりまして、こんな祟りを働くのでございます。」
———————————————-
「こんな祟り」とは、紫の上に物の怪としてとりついて殺そうとしていることを指します。それに対して光君(この時点で46、7歳)の態度はこうです。
———————————————-
‐現世の人間でいらしった時でさえ不気味な所のあったおん方の、まして今では別な世界に生を受け、怪しい変化の姿をしておいでになるのを思いやり給うと、ひどく疎ましくなりますので‐
———————————————-
だいたいからして光君の栄華の極みの象徴である六条院は、内親王だった御息所から、その娘を後見して帝に嫁がせた(秋好中宮)ことによって手に入れた敷地の上に建つのです。にもかかわらず、さらに、こんなです。
———————————————-
‐中宮のお世話をなさるのまでが今はもの憂く、詮じつめれば女というものは皆罪障の基になるものなのだと、なべての世の中が厭わしくおなりになる‐
———————————————-
もう、徹底的に御息所が悪い。これには理由があって、当時の平安貴族の心理のよりどころは仏教ですから、物の怪になった以上、やはり御息所が悪い。『窯変・源氏物語』の作者・橋本治氏は、この、平安貴族たちの心理状態を仏教本位制と呼びました。仏教(当時の呼称は仏法ですが)の教えからはみ出ることなく判断をあえて停止して生きる、という姿勢です。
当時の平安貴族がどれほど仏教に拠っていたかというのは、御息所の物の怪が言う、次のセリフでわかります。光君に、こう娘に伝えてくれ、と御息所は言います。
———————————————-
「斎宮でいらっしゃいました時のお罪が軽くなるように、功徳を積むことを必ずお忘れなさいますな。残念なことでございました。」
———————————————-
御息所の娘(秋好中宮)は12歳からの10年間ほど、伊勢の斎宮を務めました。斎宮とは天皇に代わって、その一代の全期間、伊勢神宮に仕える皇室女性のことです。当然その期間は仏事から離れることになり、御息所は娘のそんな状況を「罪」であり「残念」だったと言っているわけです。
そしてこの仏教本位制が、「彼らが謝らない」おおかたの理由です。キーワードは「宿世」あるいは「前世」です。
光君はスーパーマン的なキャラクターですから極端に「謝らない」。なので、そうではない脇役、ここでは、柏木という登場人物(前・頭中将の長男。光にとっては義理の甥。息子・夕霧の親友)の謝らなさ加減を見ていきたいと思います。
源氏物語中、最も事件らしい事件を起こすのが柏木です。若菜・上の終盤あたりで登場し、若菜・下を経て柏木という名の帖が次に続きます。簡単にいうと、柏木は光源氏の妻・女三宮を寝取り、子を生ませます。この子どもが後、宇治十帖の主人公となる薫です。
当稿からは離れますが、実はここにきわめて興味深い、非常に過激な仕掛けがあります。光、そして夕霧は、いわゆる父方に天皇の血を引く万世一系(光と藤壺との不義の子は後に冷泉帝となるが、光は桐壺帝の実子なので問題なく冷泉帝は万世一系)ですが、光の一族は皇籍ではないにしろ、異種血縁の薫が紛れ込むことになる。源氏54帖にこの伏線の活かされた帖はありませんが、夢浮橋以降に紫式部が用意していた物語がもしもあるならば、壮年の薫が描かれるにおいて重要なテーマになっていたことはまず間違いないでしょう。光が亡くなったあとの物語の主人公に選ばれたのは夕霧ではなく、とにかく薫でした。このことについてはまた別の機会といたします。
柏木の事件当時の状況をまず説明しておきます。光源氏は46、7歳。准太政天皇の地位にあり、朝廷の全人事権を掌握する、皇室外戚の最高権力者です。六条に広大な敷地の邸を持ち、関係した女性たちのほぼすべてを住まわせている。邸の女王は連れ添ってすでに25年ほどになる光最愛の紫の上(若菜・下の時点で本厄の37歳)です。そこにはまた、光の兄の朱雀院から後見を頼まれた三女・女三宮が嫁いできています。実質上、六条の邸の女王は紫の上ですが、身分上では、なにしろ内親王ですから女三宮がはるか上に位置する。紫の上の寿命を縮めた心痛の理由です。
この状況を背景にして柏木が起こした事件を整理すると次の通りです。柏木の年齢は不明ですが、夕霧の少し下の設定なので24、5歳。
1) 女三宮(事件時ハタチそこそこ)の居室から子猫の唐猫が逃げた拍子に誤って御簾が上がり、蹴鞠をしに訪れていた柏木が女三宮の姿を垣間見てしまい、恋を患う。
2) 光君には最愛の紫の上がいて、女三宮は光から大事にされておらずに辛い思いをしている、と柏木は心理的アリバイを自らの心に醸成する。
3) 柏木は女三宮の女房のひとり(小侍従)に、女三宮の寝室に手引きをするよう伝えるが叶わない。柏木は一計を案じて唐猫を手に入れ、残り香を頼りに女三宮の身替りとしてその猫を可愛がり、さらに思いをつのらせる。
4) 紫の上が重体となり、六条邸から二条邸に移されて、光はその様子見のため留守がちになる。柏木、女三宮の姉・二宮(落葉宮)を娶る。
5) しつこい柏木に小侍従はついに折れ、女三宮の寝室に手引きしてしまう。柏木は女三宮の寝室で猫の夢を見る。猫の夢は懐妊の象徴という説と不吉の象徴という説とある。
6) 女三宮は妊娠する。柏木は盛んに文を送るが女三宮は光を恐怖して会おうとはしない。
7) 光が柏木の文を見つけてしまい、ことを知る。柏木は笛の名手。朱雀院の五十の賀の楽奏の用意にかこつけて柏木を六条に呼び、無理やり酒を飲ませなどする。
8) 酒を無理やり飲まされた晩から柏木は危篤状態となる。
9) 女三宮は男子(後の薫)を出産し、直後に父の朱雀院に頼み込んで出家する。
10) 柏木、死ぬ。
だいたい二年ほどの間の出来事です。女三宮が出産した男子が光の胤ではないことを知っているのは、女三宮本人と小侍従と光の三人のみ。この小侍従が老いて尼となってから薫に出生の事実を告げる役目をします。(訂正・薫に出生の秘密を告げるのは柏木の乳母の子・弁でした。このページをご閲覧の方からご指摘をいただき、訂正を申し上げます。ご指摘に感謝いたします。不勉強の自戒をもって、元の誤りはそのまま残します。)
さて、柏木の事件は、柏木が我慢すれば何も起こらなかったわけですが、我慢をしなかった理由というか原因を、女三宮に向かって柏木はこう言います。
———————————————-
「やはりこうして逃れられない深いおん宿世があったのだとお諦めなさいませ。自分ながらも正気ではなかったような気がいたします。」
———————————————-
自分は悪くない。宿世、つまり前世からの因縁、決まっていたことなのだ、と柏木は言うのです。つらいことばかりになるならば悲劇に、よいようになれば幸福になるだけであって、反省すべき点は何もない、西洋近代的に言えば運命だというわけですが、実はここには大きなからくりがあります。
ことに及ぶ前、柏木は女三宮にこんなことを言います。身体をひき寄せるための口説き文句です。
———————————————-
「(中略)年月が立つほど、口惜しくも、辛くも、恐ろしくも、悲しくも、さまざまに深く思いがまさりますのに怺(こら)えかねまして、こう、身のほどを知らないところをお目にかけましたものの、思慮の足りない、申しわけのないことだとは存じておりますので、もうこれ以上罪な心はさらさらないのでございます。」
———————————————-
自分が悪い。それはもう知っているから、これ以上、悪いことはしない。何もしないから身をまかせてくれ、と言っているのです。こういう口説き方も当時のステレオタイプで、これこれこういうわけだから何もするわけないじゃないか、と言って抱き寄せるのが定石なわけなんですが、柏木のユニークは、この口説き文句の中に「申しわけのない」という意味が入っているところです。
柏木は、こういうときには申しわけないと考えるものだ、自分には他にしようがあったと考えるものだということを、ちゃんと知っている。しかし、結論は「逃れられない深いおん宿世があったのだとお諦めなさいませ」なのです。これはまったく文字通り仏教本位制という制度の利用であって、実に柏木はまったくうまくやっているのです。
何のために利用するのか。安定のためにです。宿世という共通了解で、以降に何が起ころうが、すべては宿世ということで了解され、争いごとにはならずに静まっていく。もちろん、積極的に、世を欺くといった態度で利用しているわけではありません。生活の知恵といった方がよほど正しいでしょう。口説き文句の中では謝ってもいいが、核心のところでは決して謝らずに宿世ということにする。謝罪や反省は時と場合によっての世過ぎのテクニックに過ぎません。言ってしまえば人のすべての行為は、宿世という言葉であらかじめ世界から許されてしまっているのです。
さて、ここに現れる宿世というものが、仏教の本来的な意味・意義の宿世、前世と同じものであるかどうかは興味深いところで、これから勉強しようと思っています。しかし少なくとも、源氏物語の、特に柏木にまつわるお話に現れる宿世は、今までお話してきたような、現世に生きる人間の安全保障のための考え方として使われていることは間違いありません。
そして、やや唐突ではありますが、私はここに日本文化の芯の強さということを思うのです。当サイトに掲載してある拙稿「源氏は国民文学か」の「九 もののあはれ、という存在論について。」で申しましたが、神話から見る日本古来の世界観は「道理は綿々とすでにどこかにある」という世界観です。上記、柏木にまつわる話に見える宿世はまさにこの世界観そのもので、日本はここでも外圧である仏教を日本に取り込んでしまっている。源氏物語に書かれてある仏教が平安仏教と呼ばれるものであるならば、平安仏教はまさに日本型の仏教です。